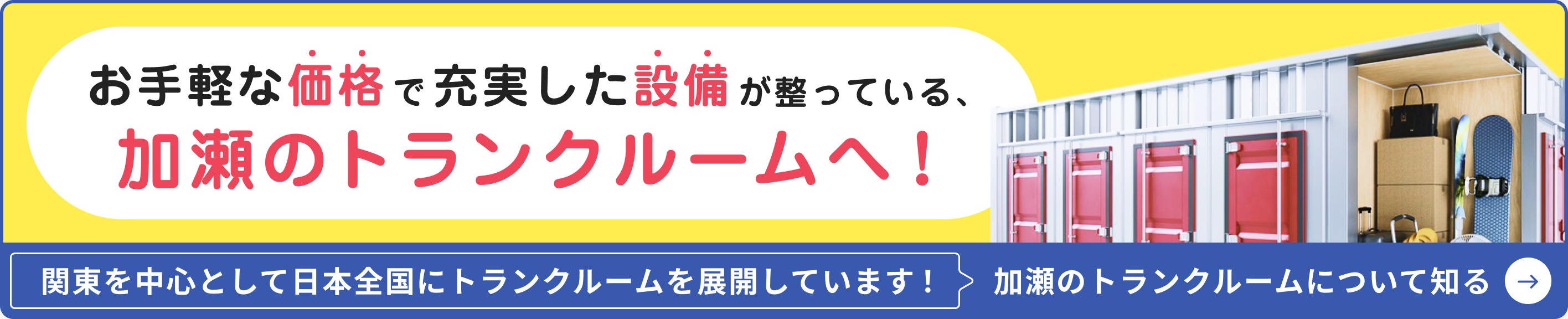五月人形は端午の節句を彩る特別な人形ですが、いつまで飾るべきなのでしょうか。また、出しっぱなしにしてよいのでしょうか。
節句を過ぎても飾り続ける場合、素材によっては人形が傷みやすくなるため、こまめに手入れをする必要があります。大切な五月人形を美しいまま保管するための注意点を紹介します。
目次
五月人形を出しっぱなしにした場合の注意点
五月人形には、「病気や事故などの災難にあうことなく、健やかに成長しますように」という思いが込められています。近年はインテリアとしても楽しめるおしゃれなデザインが増え、「せっかくだから年中飾っておきたい」と思う方も多いでしょう。
実際のところ、五月人形は端午の節句を過ぎても飾っていて問題ありません。ただし、長期間の展示を想定していない素材の場合は、劣化を防ぐために少し注意が必要です。
たとえば、顔や手足に胡粉(ごふん)が塗られた人形や、漆(うるし)仕上げの兜や鎧は、乾燥や日光に弱いため、定期的にホコリを払ったり、直射日光を避けたりするなどのケアを心がけましょう。
一方で、陶磁器製でホコリがつきにくい人形や、樹脂製で水拭きできるタイプなら、ケースに入れて長期間飾っても問題ありません。
出しっぱなしで楽しみたい場合は、まずは人形の素材を見極めて、扱い方を変えることが大切です。素材に合わせたお手入れをすれば、五月人形を長く美しいまま飾っておくことができます。
五月人形をしまうタイミングはいつ?
五月人形をしまうベストなタイミングは、端午の節句(5月5日)が終わってから、5月末までの間です。4月中旬〜下旬に飾り付けた場合は、2〜3週間ほど楽しんでから片付けるのが目安です。早めに出して長く飾りたい場合は、3月中旬から飾り始め、5月末頃にしまうと良いバランスになります。
5月末までに片付けを済ませたい理由は、6月に入ると梅雨で湿気が多くなるためです。湿度の高い日に収納してしまうと、人形にカビやシミが発生するリスクがあります。
晴れた日を選んでホコリを払い、しっかり乾燥させてからしまうのが理想です。
また、「仏滅にしまうと縁起が悪い」といった日柄の決まりはありません。端午の節句を終えたら、5月中の晴れた日に丁寧に掃除してしまうのが一番安心です。
五月人形の収納に役立つ便利アイテム

五月人形をしまうときは、人形を傷つけないように丁寧にお手入れをしてから収納することが大切です。ここでは、五月人形をきれいな状態のまま保管するために役立つアイテムを紹介します。
手袋
五月人形をお手入れするときは、白い布手袋をつけるのがおすすめです。素手で触ると、手の油分や汚れが人形に付着してしまい、シミや変色の原因になることがあります。
特に、顔や金属パーツなど汚れが目立ちやすい部分に触れるときは注意が必要です。手袋をつけていれば、指紋がつく心配もなく、汚れの有無も目で確認しやすくなります。
布手袋は100円ショップやホームセンターでも手軽に購入でき、五月人形だけでなく雛人形や仏壇の掃除にも使える便利アイテムです。飾りつけるときや片付けるときの両方で活躍するので、シーズン前に用意しておくと安心です。
はたき
五月人形の表面にうっすら積もったホコリは、羽毛など柔らかい素材のはたきを使ってやさしく払います。
力を入れず、ふわっとなでるように動かすのがポイントです。細かい装飾部分やすき間は、先をほぐした筆や小さなブラシを使うとより丁寧に掃除できます。
顔や着物にホコリが残ったままだと、シミや虫食いの原因になることもあるため、見落としがないように確認しましょう。
収納前にしっかりホコリを落としておくことで、翌年もきれいな状態で飾ることができます。
綿棒
はたきでは届きにくい細かな部分のホコリ取りには、綿棒が便利です。特に兜の飾りや刀の持ち手など、金属や装飾の細かいパーツを掃除する際に役立ちます。
汚れが気になる場合は、綿棒の先をほんの少し湿らせて軽く拭き取り、仕上げに乾いた布で水分をしっかり取り除きましょう。水気が残るとサビや変色の原因になるため、掃除のあとは風通しのよい場所で十分に乾かすことが大切です。
綿棒を使うときは、力を入れずにやさしくなでるように動かすのがポイントです。細部まで丁寧に掃除すれば、人形の美しい艶や質感を長く保つことができます。
人形を包む布や和紙
手入れを終えた五月人形を包むときは、湿気を防ぎつつ通気性のある布や和紙を使いましょう。新聞紙やチラシはインクや油分が人形に移るおそれがあるため避け、無地で柔らかい素材を選ぶのがおすすめです。
購入時に人形が包まれていた布や和紙が残っている場合は、そのまま再利用してOK。ただし、黄ばみや破れがあると逆に汚れや繊維が付着することがあるので、気になるときは新しいものに取り替えましょう。
包む際は、顔や手足などの細かい部分を軽く覆うようにして、隙間を作らずふんわり包むのがポイントです。こうすることで、人形をやさしく守りながら長くきれいな状態を保てます。
五月人形を長持ちさせる収納のコツ

五月人形を長くきれいに保つためには、掃除だけでなく収納の仕方にも気を配ることが大切です。しまい方を誤ると、カビや変色、部品の破損などにつながることもあります。
ここでは、来年も安心して飾れるようにするための収納のコツを紹介します。
顔や手足を傷つけないようにする
五月人形を収納するときは、顔や手足を傷つけないようにやさしく保護しましょう。顔や手足の部分は特に繊細で、少しの衝撃でも欠けたりヒビが入ったりしやすいため、柔らかい布や和紙で軽く包んでから箱に入れるのが安心です。
特に、顔や手足に貝殻から作られた胡粉(ごふん)が塗られている人形はデリケートな仕上げになっているため、直接触れないよう注意が必要です。
包むときは、力を入れずふんわりと包むのがポイントです。さらに、箱の中で動かないように紙やクッション材を周りに詰めて固定すると、保管中の揺れや衝撃から人形を守ることができます。
日光が当たらない場所に保管する
五月人形は、直射日光に長時間当たると色あせや変色の原因になります。保管するときは、日が差し込まない押入れや納戸、クローゼットの奥など、暗くて風通しのよい場所を選びましょう。
また、これは保管時だけでなく飾るときも同じです。玄関や窓際など、日差しが直接当たる場所は避け、レースのカーテン越しや部屋の奥側など、やわらかい光が入る位置に飾ると安心です。
人形専門の防虫剤を使用する
虫食いを防ぐためには、人形専用の防虫剤を使うのが安心です。ただし、使う場所や種類・量を誤ると、人形を傷めてしまう原因になることもあるため注意が必要です。
たとえば、兜や鎧などの金属部分に不向きな防虫剤もあり、種類によっては発生したガスでメッキが浮いたり、
プラスチック製のパーツが溶けたりすることがあります。
防虫剤を選ぶときは、購入したお店やメーカーに対応する製品を確認しておくと安心です。使用する際は、人形に直接触れないように配置し、入れすぎないよう適量を守ることが大切です。
湿気が少なく風通しの良い場所に保管する
五月人形をしまうときは、気温差が少なく湿気のこもりにくい場所を選びましょう。湿気は人形の大敵で、結露が起きやすい場所ではカビや錆びの原因になることがあります。
とくに、金具を使った兜や鎧は結露によってサビつくこともあるため注意が必要です。押入れに収納する場合は、湿気がたまりやすい下段よりも、風通しのよい上段に置くのがおすすめです。
もし人形が重くて上段に置けない場合は、除湿剤を併用して湿気対策をしておきましょう。季節の変わり目に除湿剤を入れ替えるだけでも、長期間きれいな状態を保てます。
正しいお手入れで、五月人形を長く美しく
五月人形は、端午の節句を彩る大切な飾り物です。きちんとお手入れをすれば、出しっぱなしでも美しい姿のまま長く楽しむことができます。
人形の素材や飾る環境に合わせて手入れをし、湿気や直射日光を避けて大切に扱いましょう。もし自宅に十分な収納スペースがない場合は、湿度管理が整ったトランクルームを活用するのも安心です。
丁寧に扱えば、五月人形は毎年きれいな姿で迎えられます。思いのこもった人形とともに、男の子の健やかな成長を穏やかに見守っていきましょう。