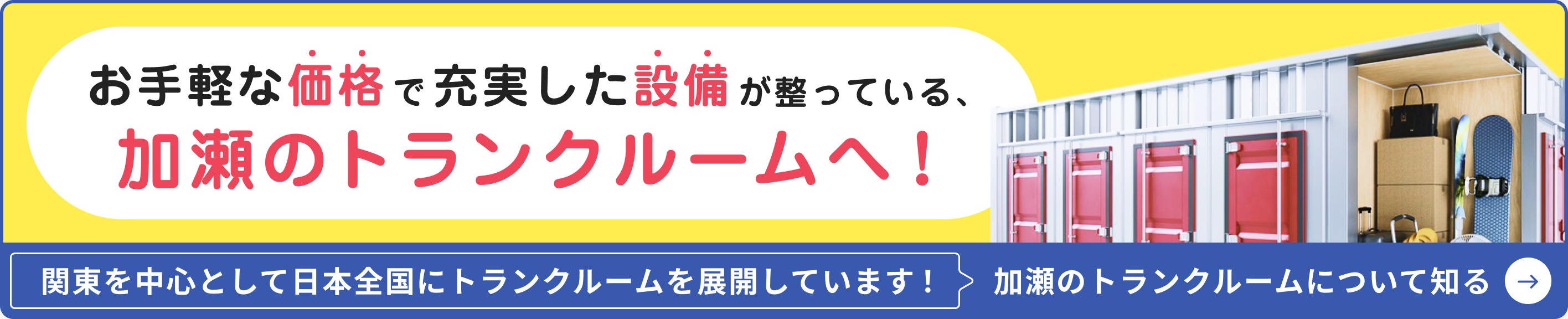クリスマスツリーはオーナメントなどもあるため、意外と収納方法に困るものです。この記事では、クリスマスツリーの収納アイデアやお役立ちグッズをまとめました。
そのほか、クリスマスツリーを収納するまでの流れやクリスマスツリーのおすすめ収納場所などもわかりやすく紹介します。
目次
クリスマスツリーの収納アイデアとおすすめグッズ

クリスマスツリーの収納に役立つアイデアとおすすめグッズを紹介します。
収納アイデアとしては、収納ボックスやバッグなどを用いる方法のほか、100円ショップのアイテムを活用する方法などが挙げられます。
IKEA「SKUBB 」
クリスマスツリーの収納におすすめなのが、IKEAの収納ボックス「SKUBB(スクッブ)」です。「SKUBB」は、季節物の衣類や寝具の収納に適しています。
なかでも、クリスマスツリーの収納に適しているのが、93×55×19cmのタイプです。開口部が広く、ツリー本体だけでなくオーナメントやLEDライトなどもまとめて収納できる収納力が魅力です。
山崎実業「tower(タワー)クリスマスツリー収納バッグ 」
山崎実業「tower(タワー)クリスマスツリー収納バッグ」もクリスマスツリーの収納に活用できるアイテムです。可動式のポケット付き仕切りが付いており、ツリーのサイズに合わせて仕切りを移動できるほか、オーナメントなどの収納にも役立ちます。
また、持ち手付きのため収納時にも便利です。クリスマスツリーのほか、アウトドア用品や衣類の収納にも活用できる収納グッズといえます。
ダイソーなどの100円ショップのアイテム
クリスマスツリーを収納する際には、ダイソーなどの100円ショップのアイテムを活用する方法もあります。たとえば、ボックス型に組み立てたパズルマットやワイヤーネットを活用すればツリー本体をすっきり収納できます。
また、チャック付き収納袋やはがきケースを活用することで、オーナメントを種類ごとに収納可能です。
無印良品の収納ケース
無印良品の収納ケースをクリスマスツリーの収納ケースとして有効活用する方法もあります。大きなふた付きボックスは、クリスマスツリーをそのまま収納したいときに便利です。
小さめのボックスであれば、オーナメントなどをまとめて収納するのに役立ちます。
クリスマスツリーを収納するまでの流れ

クリスマスツリーを収納するまでの流れについても押さえておきましょう。
主な流れは次のとおりです。
- オーナメントを取り外す
- クリスマスツリーのほこりを払う
- ライト類をまとめる
それぞれ詳しく紹介します。
オーナメントを取り外す
まずは、オーナメントを取り外しましょう。オーナメントは大小さまざまなサイズがあり、壊れやすい素材のものもあるため、取り扱いに注意しながら小分けにして収納するのがおすすめです。
種類ごとに半透明の袋に入れておけば、中身がわかりやすいため、翌年使用する際にも便利です。
クリスマスツリーのほこりを払う
続いて、クリスマスツリーを収納する前にツリーに付着したほこりを払いましょう。
ほこりが付いたまま収納すると、ツリーにカビが発生する原因になります。また、拭いた箇所は、収納前に乾燥させることが重要です。
しっかりと乾燥させたあとに大きさに応じて枝を分解しましょう。枝をまとめて収納すればスペースを節約できるだけでなく、翌年飾る際にも取り出しやすくなります。
クリスマスツリーを収納するケース類を購入する場合は、一番長い縦幅を計測してそれに応じたサイズのケース類を購入しましょう。ツリーの葉は意外と自由に動くため、横幅は融通が利きやすい傾向にあります。
ライト類をまとめる
クリスマスツリーと同様にライト類やコード類もひとまとめにしてから収納しましょう。その際も、付着したほこりや汚れを拭き取って水分が残らないように乾かしてから、収納することが重要です。
なお、コード類は絡まらないようにまとめて収納するようにしてください。
クリスマスツリーを収納する際の注意
クリスマスツリーを収納する際にはいくつか注意点があります。ツリーを長持ちさせるためには、湿気やほこり、直射日光を避けて保管することが大切です。
高温多湿の場所に保管すると、カビや劣化の原因になります。また、ほこりが付着したままでは、ダニが繁殖しやすくなるため注意が必要です。
さらに、直射日光が当たる場所にツリーを置いておくと変色する恐れがあります。
これらのリスクを避けるためにも、収納方法や収納場所には十分気をつけましょう。
クリスマスツリーを出す時期・片付ける時期

クリスマスツリーを出す時期・片付ける時期についても確認しておきましょう。キリスト教における習慣と日本における習慣では違いがあります。ここでは、両者の違いもあわせて紹介します。
クリスマスツリーを飾り始める時期
キリスト教では12月25日の4週前の日曜日から、イエス・キリストの降誕を迎えるための準備期間(待降節)としています。そのため、待降節の始まる日曜日にクリスマスツリーの飾り付けを始めることが多いようです。
とはいえ、日本では伝統的にキリスト教を信仰する習慣も少ないため、10月31日のハロウィンが終わり11月上旬ともなれば、街並みはすっかりクリスマスモードに様変わりします。各ご家庭でのクリスマスの装飾時期にも特に決まったルールがあるわけではないので、自由に始めて問題ありません。
クリスマスツリーを片付ける時期
キリスト教では12月25日から1月6日までをクリスマス休暇として、イエス・キリストの誕生を祝う習慣があります。そのため、1月6日まではクリスマスツリーが飾られているのが一般的です。
しかし、日本では少々事情が異なります。12月25日のクリスマスが終わったら、お正月にむけて門松・しめ飾り・鏡餅などの準備をしなければなりません。これらのお正月飾りは12月28日までに飾るのが良いとされているため、クリスマスツリーの片付けも12月28日までには終わらせたいものです。
クリスマスツリーのおすすめ収納場所

クリスマスツリーのおすすめ収納場所を紹介します。おすすめの場所としては、次の4つがあげられます。
- 室内のデッドスペース
- 押し入れやクローゼット
- 物置や納戸
- トランクルーム
それぞれの特徴を把握して、自身に合った収納場所を見つけましょう。
室内のデッドスペース
室内のデッドスペースを活用してクリスマスツリーを収納する方法があります。室内のデッドスペースとして考えられるのは、ベッドの下や掃除用具入れ、使用していない収納スペースなどです。
ベッドの脚が高い場合は、ベッド下のスペースを活用すればクリスマスグッズをまとめて収納できるかもしれません。ただし、ベッド下は通気性が悪く湿気がこもりやすい場所のため、定期的な換気や除湿が欠かせません。
また、掃除用具入れや使用していない収納スペースなどであっても、室内は基本的に温度や湿度があがりやすい環境です。そのため、ツリーの収納場所が高温多湿にならないように注意しましょう。
押し入れやクローゼット

クリスマスツリーの収納場所として、押し入れやクローゼットを活用する方法もあります。クリスマスツリーは年に一度しか使用しないアイテムであるため、押し入れやクローゼットにまとめて収納するのがおすすめです。その際、キャスター付きの台などに載せて収納しておくと取り出しやすくなります。
ただし、押し入れやクローゼットも湿気がこもりやすい場所です。定期的に換気を行ったり除湿剤を設置したりするなどの湿気対策を行うようにしてください。
物置や納戸
自宅に物置や納戸があるのであれば、そこにクリスマスツリーを収納してしまう手もあります。そうすれば、押し入れやクローゼットのスペースを有効活用できるようになるでしょう。
物置や納戸は湿気がこもりやすいほか、外気温の影響を受けやすい場所です。定期的に空気の入れ替えを行ったり除湿剤を活用したりするだけでなく、すのこなどを活用して万全の湿気対策をするようにしましょう。
トランクルーム
自宅にクリスマスツリーの収納場所がないという場合は、トランクルームの活用も有効な手段といえます。トランクルームとは、収納スペースをレンタルできるサービスです。トランクルームにクリスマスツリーを預ければ、そのぶん自宅内の収納スペースを確保できます。
トランクルームには屋外型と屋内型があり、それぞれ特徴が異なります。屋外型は同じ広さのスペースでも屋内型と比べて利用料金が抑えられるケースが多く、シーズン用品の長期保管におすすめです。一方の屋内型は、空調設備が行き届いているケースが多く、温度や湿度の管理が求められる物の保管に向いています。
「加瀬のレンタルボックス」では用途に応じて屋外型、屋内型それぞれを選択可能です。住所やタイプ、広さなどから自宅近くのトランクルームを検索できるため、ぜひご活用ください。
長持ちする方法を選んでクリスマスツリーを収納しよう
クリスマスツリーは本体以外にもオーナメントやコードなどがあるため、収納場所に困りがちです。この記事で紹介した収納アイデアやおすすめグッズを活用して、クリスマスツリー収納に挑戦してみましょう。
また、自宅でクリスマスツリーを収納するのに適した場所としては、室内のデッドスペースや押し入れ・クローゼット、物置・納戸などがあげられます。自宅の限られたスペースではクリスマスツリーを保管できないという場合は、トランクルームの活用もおすすめです。
「加瀬のレンタルボックス」であれば、用途に合わせて屋外、屋内それぞれを選択できます。大切なクリスマスツリーの保管にぜひご活用を検討ください。